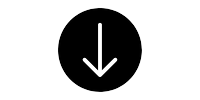#01 フリーダムでマイペースなオコジョのような茶色いキツネ – おこもり奇譚(長編小説 / 現代ファンタジー)

前の話
担任への挨拶をトリガーとして、本日も滞りなく放課後が始まった。あふれる解放感。わき立つ喧噪。それらに背中を押されるように、クラスメイトたちが立ちどころに廊下へと流れ出す。俺もひとり、はやる気持ちを抑えながら、何食わぬ顔でその中に混ざり込んだ。
大多数の生徒が正面玄関へと向かい、それ以外の生徒が数人単位の塊となって壁際に散在していく中。俺はといえば――。
「おいおいおい、ふざけんな……! バイトに遅刻するだろうが……っ!」
帰宅を急ぐ生徒の波を逆流しながら、脇目も振らずに廊下を疾走するという超少数派な存在として、今まさに若干の注目を集めている。
不審げな視線が肌にちくちく刺さるのを感じながらも、俺は走ることをやめられない。いや、迷惑なのはわかってるよ、ごめんなさいね。けど、俺だって好きでこんなことしてるわけじゃないからな。
自慢じゃないが、俺は特別に足が速いわけでも、特別に容姿が優れているわけでもない。なので、今のように瞬間的に悪目立ちをしても、あっという間に存在を忘れ去られる。地味な人間だけが持つ特異な能力として、今後とも有効に活用していきたいところだ。
が、中には、そんな俺のことすら気にしてくださる、お優しくて時間に余裕のある方々もいらっしゃるわけで。
――アイツ、ホラ。
――アア、レイノ。
――アレデショ、五クミノ。
いわゆる、カクテルパーティー効果ってやつだろうか。自分に関係のある言葉は、騒がしい場所でも自然と聞き取れてしまうという現象。望むと望まざるとにかかわらず。
明らかな嘲笑がハウリングのように弾みながら、廊下を抜けて一号館を離脱しようとする俺の後をしつこく追ってくる。
自分たちがどんなに幸運な境遇にいるのかも知らずに、好き勝手なこと言いやがって。
狐守の家系に生まれていたら、お前らだって俺と同じ目に遭っていたんだぞ――などと、懇切丁寧に説明してやる義理は、当然ながら、ない。
言いたい奴には言わせておけ、をモットーとしている俺はギアをひとつ上げて、耳障りなノイズを振り切るべく、走る。
一号館に隣接する三号館も通り抜け、正面に多目的会館、右手に駐車場が見える開けた場所へと辿り着く。俺の帰宅部かつインドアな部分が、ここに来て、とうとう露呈した。足を止めた勢いのまま両膝に両手を置き、全身を使ってしばしの酸素吸入タイムに突入する。
相手の事情を欠片も考えない幼稚な陰口にはもう慣れたと思っていたが、案外そんなことはなかったのかもしれない。うっかりイラッとして、ついつい全力ダッシュをしてしまったことは認めよう。
呼吸を整えながら、腕時計に視線を送る。バスの発車時刻まで、ほとんど余裕がない。あと五分で探し出し、学校を出なければ。そう算段を立てた俺は、最後にひとつ息を吐くと、気合いを入れて背筋を伸ばした。
「どこに行きやがった、あいつ……」
探し物は、いつも同じ。けれど、いつも同じところにいるとは限らない。ただ、だいたいの居場所だけなら何となくわかってしまう。勘の延長のような、不確かな感覚ではあるが。
ここは、中庭を中心として一号館や二号館などの教室棟だけで構成された四角い空間から、少し外れたところにあった。目の前にある多目的会館をはじめとして、第二体育館や部室棟、弓道場やサイエンス館といった、多種多様な施設への分岐点かつ通過点になっている。
それはつまり、好奇心旺盛なあいつが興味を惹かれて思わずふらふら入り込んでしまいそうな場所が無数に存在する、ということだ。視界の中にあるだけでも、建物の数は余裕で片手の指を上回るうえに、駐車場では色とりどりの車があちらこちらで咲いている。
これ以上、走り回ったり、ましてや覗き込んだり、這いつくばったりしながら周囲を捜索するという選択肢は、当然ながら俺にはない。絶対にない。そもそも、しらみつぶしをするには圧倒的に時間が足りない。
――なので、探し物のほうから出てきてもらうことにする。
念のため辺りを見回し、誰もいないことをしっかり確認する。もう既に変人として一部で名が知られているのは理解しているが、ただの変人から、やばい変人に認識のレベルを上げられても面倒くさい。
すぅっと息を吸い込み、だだっ広い空間に向かって俺なりの精一杯の声を張り上げようと胸を逸らし――いざ、
「きゅ……!」
「――筒井」
いや、それはだめだって。そのタイミングで声をかけてくるのは絶対だめだって。
ヤッホーの要領で手でメガホンまで作った気合い十分な呼びかけを途中で邪魔されてどうしていいかわからずに固まっている今の俺の気持ちになって考えてみたらわかるから。本当に申し訳ないことしたって心の底からわかるから。
「筒井、おーい?」
「……登場がいつもいつも唐突だっつっても流石に限度があるわ、在里お前!! どこにいた!」
「そこの柱の裏。いつ話しかけようか、ずっと迷っててさ」
「そのままずっと迷ってろ! なんでよりにもよって今をチョイスした!」
在里が指を差した先にある柱は、俺が背にしている三号館側にあり、ちょうど死角になっていた。自分のうっかり具合を呪うと同時に、なんでこいつはそんなとこにいたんだと、たぶんに八つ当たり気味な怒りが湧いてくる。まあ、それが照れ隠しからくるものだということは自分でも承知しているので、その苛立ちはひとつの溜息とともに簡単にどこかへいってしまったが。
「悪い悪い。きょうも探し物か?」
あくまでも純粋に、どこまでも爽やかに、そいつは笑う。
おそらく、新緑の季節の風とか、水面に反射する光とか、そういう穏やかさの象徴みたいなものをひとつにまとめて丁寧に細工を施せば、こういう人間ができあがるんだろう。
それが俺の、在里颯真に対する印象だ。端的に言えば、俺とは住む世界が真逆な人間。学校の端と端、対角線上にいるような存在。同級生ではあるが、クラスは違う。当然、接点などないから会話をする理由もない。ないはずだ。
にも関わらず、こいつは今のように簡単に話しかけてくる。
「手伝う?」
「だからいらねーっていつも言ってんだろ、帰れ帰れ。ってか、お前、部活じゃないのかよ」
「ああ、うん。今日は、ちょっとな」
放課後に遭遇するときは、こいつはいつもジャージを着用していたと思ったが、今は俺と同じ夏仕様の制服だ。部活自体が休みなのか、それとも単純に在里がサボっただけなのか。後者であれば、らしくないとは思うが、どちらにしても、そこまで興味はない。
むしろ、暇な在里が、このままずっとここに居座り続けてしまう可能性が高まったことに焦りを感じた。探し物に対して呼びかけるという手段が使えないまま、今この瞬間にもバスの発車時刻はどんどん迫ってきている。とにかく駐車場のあたりに絞って探し始めようと、俺は在里を放置し、ある程度の距離をとってから捜索を再開した。
「懐かしいな。俺も見てたよ、ヤイバーマン」
急に何の話を始めたのかと、眉をひそめながら在里を振り返れば、奴の視線は俺の手元にまっすぐ注がれている。今更ながら、そこで俺は自分がずっと水筒を持っていたことに気付いた。
子どものおもちゃのような水筒を、バトンのごとく片手で大きく振りながら廊下を全力ダッシュする男子高校生。それはそれは、傍から見れば口をぽかんと開けたくもなるような、さぞ異様な光景だったことでしょう。
「刀で戦うのが、かっこよかったよな。友達と一緒に傘を振り回してたら、危ないだろうって祖母に怒られた」
「意外。お前でも、そんなことすんのな」
車体の下を覗き込み、タイヤの上を確認しながら、俺は適当に返事をする。俺とは住む次元が違うような爽やかイケメンでも、俺と同じものを見て、俺と同じようなことをして遊んでたのかと思うと、なんともいえない妙な感じだ。
「筒井は、やっぱりヤイバーレッドが好き?」
「やっぱりってなん……ああ、コレか」
そういえば、赤だったか。片手に持っていた年季の入った水筒が、ヤイバーレッドの象徴色を基調としているのを確認して、俺は納得する。
「どうだったかな、忘れた」
「弱気を助け強きを挫くっていう、これぞ主人公という感じの熱いキャラだったよな、レッドって。お人好しすぎて見ていてハラハラすることもあったけど、決めるところはバシッと決めるのが本当にかっこよかった。なんだっけ、あの必殺技……ええと、さ、ささくれ――」
「灼熱紅蓮乱舞鳳凰斬な。次、間違ったら泣かす」
やばい。在里の熱い語り口に乗せられて、ついつい当時得た知識を食い気味で披露するどころか脅しまでかけてしまった。まさか今の一言で、毎週テレビにかじりつくようにしてヤイバーマンを見ていた俺の幼すぎる過去がバレるようなことはないと思うが。
「そうそう、しゃくねつぐれんらんぶほうおうざん。俺もよく真似してた覚えがある」
「本当かよ。その言い方は絶対に漢字で書けないやつだろ。……まあ、確かにお前はレッドが好きそうだよな」
正統派なヒーローを体現したような在里なら、当然、同じような人物を好きになるだろう。根拠の薄すぎる見解を適当に飛ばしながら、駐車場脇の茂みの辺りを覗き込む。マジでどこに行ったんだ、あいつは。
「俺? もちろん、レッドもブルーもグリーンもホワイトもゴールドも好きだけど、一番はブラックかな」
「ブラック!?」
ちまたではクールで通っているに違いない俺が思わず上擦った声を上げ、あれほど急いでいた捜索の手もぴたりと止めて、思いっきり力を込めて振り返るくらいには、その返答は意外だった。
「ブラックって、あのブラックか? 陰気で根暗で無口で無愛想で協調性が皆無でいっつも単独行動をしていたから視聴者にまで不審がられて最終話寸前までラスボス疑惑をかけられていた、あのブラ――」
唐突に。
探し物が、見つかった。
今日は珍しく水筒の中で大人しくしていると思っていたら、いつの間にか逃げ出していたあいつが。
バイトに遅刻寸前という俺の切羽詰まった状況など露知らず、今の今まで呑気に遊び歩いていた、フリーダムでマイペースなオコジョのような茶色いキツネが。
――在里の肩の上に、ちょこんと乗っていた。
「キュー!!」
「ブラッキュ?」
「きゅ?」
俺の叫びを浴びた在里とキツネが、同じタイミングで、同じ角度で首を傾げる。いや、仲良しかお前ら。
なんでよりによってそんなところに、と思わなくもないが、目的のものが見つかったことで、とりあえずは安堵の息を吐く。あとは、気まぐれなキツネが、またどこかに逃げてしまう前に、とっとと捕まえればいい。
「はは、そんなに驚かなくても。ブラックにだって、いいところはあっただろ? それにしても本当に詳しいな、筒井」
キツネが見えていない在里は、どうやらまだヤイバーマンの話を続けるつもりでいるらしいが、俺はもうお前の肩に乗っているキツネのキューちゃんを捕獲することしか考えてないんだ。悪いな。
「ちょっとそのまま動くなよ、在里。ついでに目を閉じて耳を塞いでいてくれれば、尚いい」
「え、よくわからないけどわかった」
わかるのかよ。素直なのか、それとも考えが足りないのか。どちらにせよ、何の疑問も抱かず俺の言われるがまま行動する在里のことが色々と心配になるが、今はキツネもどきのオコジョを回収するのが先だ。いや、オコジョもどきのキツネだったか。どっちでも大して変わらない。
わざわざ迎えに来てやってるというのに、キューちゃんは在里に興味津々のようで、徐々に距離を詰めていく俺に対しても、まったく注意を払わない。あまつさえ、在里の顔を正面から堂々と覗き込んだり、頬のあたりに頭をこすりつけはじめる。
「おいやめろ、スリスリすんな。さっさとこっちに来い」
「きゅ! きゅ!」
すっかりその場所が気に入ったのか、普段から俺の言うことなど全く聞かないキツネは、ここでも断固拒否の姿勢を見せた。イヤイヤするように頭を振って、在里の首の裏側へと回り込み、完全に視界から消えてしまう。
苛立ちながら腕時計に目をやれば、いよいよ時間がない。こうなったら力づくで引きはがそうと、大きく足を踏み出して腕を伸ばした、そのとき――。
突風が、吹き抜けた。
在里の首の辺りから、かろうじて覗いているキューちゃんの尻尾。
それを捕まえるために伸ばした右手が、在里の顔の横を通過する、直前。
「っ!?」
――目に見えない低反発クッションのような風圧に、横から殴られるように、弾かれた。
前触れのない自然のきまぐれに驚いて周囲を見回すが、所々に点在する木々の揺れに異常はなく、空は青く晴れたままだ。第二波を警戒してしばらく動きを止めてみたものの、遠くで風が暴れているような音も聞こえない。
なんだったんだ、と疑問符を浮かべる俺の頭上に、いつの間にかキューちゃんが飛び乗ってきていた。「きゅ、きゅ」と何やら興奮して騒いでいるが、デフォルトなので放っておく。
「筒井、大丈夫か……?」
視覚を閉ざし、聴覚まで封じていた在里でも、自分の眼前を駆け抜けていった強い風には気付いたのだろう。すぐ近くから聞こえてきた、焦りの響きを帯びた声に驚いて顔を向ければ、こちらを見つめる在里の気遣わしげな目と、目が、あう。
「……っいや、ただの風だろ。んな、心配することでも」
「そう、だな……」
突風どころか天変地異が起ころうとも、凶悪怪獣が出現しようとも、全く動じることなく笑っていそうな在里が。ただの風に、ここまで過剰な反応を見せていることに少なからず違和感を覚えるが、それ以上に……なんというか。女性的とは言えないが、男性的とも言いづらい、小さく整った顔が至近距離にあるというのが……すこぶる、居心地が、悪い。
「けがを――」
「してないしてない。……お前、なんか変だぞ」
こいつはいつだって変だが、きょうの変は変の種類が違う。俺は、わずかに痺れているだけの右手を、無傷の確認という意味と、在里の視界を遮るという意図をもってかざしてやる。それを盾に、こっそりと一歩だけ下がることも忘れない。
「そうかな……あ、探し物は?」
「見つかったし、回収した」
「きゅ!」
「なら、よかった」
在里に、ようやく笑顔が戻る。回収されました! とばかりに嬉しそうに返事をしたキューちゃんが、俺の頭頂部をてしてし叩いているのが心底うっとうしいが、いつものことなので気にしない。――それにしても。
「……お前さ。いつもそんな感じで軽く流してるけど、この状況に疑問とかないわけ?」
「疑問はないけど、質問はあるかな」
「なに」
「筒井って、レインしてる?」
レイン――携帯電話を持っている奴なら、老若男女問わず誰もが知っているに違いない、超有名なコミュニケーションアプリだ。俺には無用の長物だが、バイト先との連絡ツールとして使うことが、たまにある。
「ほとんど使ってないが、まあ一応。それがなんだ」
「俺と、アドレス交換してくれないかなって思って」
「…………は? なんで?」
友達でもないのに。という言葉こそ口にはしなかったが、それはお互いの共通認識だと思っていた。たまたま出会えば、なぜかほんの少しだけ会話をする程度の、ただの変人同士。日常的に連絡を取る必要性を、少なくとも俺のほうは全く感じない。
「いや、ちょっと――」
在里が言いづらそうに口をつぐむ様子を、まじまじと伺ってしまう。バスの発車時刻というタイムリミットが迫っていることがわかっていながら、思わずその先の言葉を待ってしまうくらいには、珍しい反応だった。
「在里!」
不意に、遠くから声がかかった。ご指名を受けた当人の視線を追いかけると、そこにはジャージを着た男子生徒が二人。おそらくは、在里と同じ陸上部だろう。こちらに向けて、ちょいちょいと手招きをしている。この場所で、待ち合わせでもしていたのだろうか。「すぐ行く」と、二人組に応える在里の横顔は、もう、いつもどおりだ。
「引き止めて悪かったな、筒井。きょうもバイトだろ?」
「……ああ、まあ。――げ」
どこか消化不良気味のまま腕時計を確認すれば、長針が予想外の数字を指し示している。これはやばい。非常にまずい。バス停まで全力で走ればなんとか間に合うか。いや、間に合わせる。
頭の上のキューちゃんを水筒の中に押し込め「絶対出てくるなよ! 絶対だからな! っつーか、勝手に出歩くなって何度も何度も何度も言ってるよな俺は!」と文句を言う時間すら惜しい。そのまま正面玄関へと走り出す俺の背に、気をつけて、という在里の律儀な声がかかる。
挨拶を返すこともなく顔だけで軽く振り返った視界の中で、穏やかに微笑むあいつの姿だけが鮮明に映っていた。